退職金計算の方法・考え方について
ここでは退職金の計算方法や計算例など、より具体的な内容になっています。お問い合わせが多い場合などは、下記以外の質問も随時追加/更新する予定です。
1.退職金設定額の考え方
本制度は、保険数理でいう「収支相等の原則」に基づいて組み立てられています。収支相等の原則とは、ある年の加入者の集団について、加入者全員が退職するまでの全期間にわたる掛金収入とその掛金を運用することによる利息との総収入額と、退職者に対して支給する退職金の総支出額とが等しくなるよう計算されているということです。
また、退職金額の設定に当たっては、収支相等の原則のもとに、勤続年数の短い者より、勤続年数の長い者を優遇する、いわゆる“退職金カーブ”を描くように設計してあります。これによって、中小企業においても長期勤続者に払い込み額の元利合計額を上回る退職金を支給できる制度にしてあります。このことから、本制度は単なる積立金制度でなく共済制度であるといえます。
なお、“退職金カーブ”の具体的内容は、中退法および中退法施行令で定められていますが、掛金を運用して得られる運用収入の額が経済情勢や金利の動向によって変動しますので、“退職金カーブ”も見直される場合があります。
2.掛金納付月数と退職金額の関連
- 1. 退職金の額は、掛金月額と納付月数によって算出した基本退職金に付加退職金を加えた額です。ただし、掛金納付月数が42月以下で退職した場合は、付加退職金は付きません。
- 2. 解約手当金の額は、上記1と同じ方法により算出いたしますが一定の方法で減額される場合があります。
- 3. 掛金納付月数が11月以下のときは、退職金も解約手当金も支給されません。(通算制度または、他制度からの引継ぎを行っている場合は、11月以下でも支給される場合があります。)
また、掛金納付月数が12月以上23月以下の場合には支払われる額は、納付された掛金総額の約2分の1から3分の1と少なくなります。 - 4. 掛金月額を増額した場合には、加入後の掛金納付月数が24月以上であれば増額後の掛金納付月数が23月以下であっても、増額分の掛金総額が支給されます。加入後の掛金納付月数が23月以下の場合は、増額後の掛金納付月数が11月以下であれば、増額分の掛金は支給されません。また、12月以上23月以下のときは、増額分の掛金総額の約2分の1から3分の1と給付額が少なくなります。
- 5. 死亡による退職の場合には、掛金納付月数が12月以上であれば、退職金は掛金総額より少なくなることはありません。
- 6. 過去勤務掛金が納付されている場合
- 過去勤務掛金を完納した場合は、本体の掛金納付月数に過去勤務期間を通算した月数とその掛金月額により算定した額が支給されます。ただし、通算して算定した額が本体の退職金額に過去勤務掛金総額を加算した額を下回る場合は、当該加算した額が支給されます。
- 過去勤務掛金を完納せずに退職または解約をした場合は、納付された過去勤務掛金の総額(納付月数が43月以上の場合は、元金に利息を付した額)に、本体の掛金に対する退職金額を加算した額が支給されます。
※平成14年10月31日以前に加入した被共済者の退職金計算
退職金の額に関する経過措置として、平成14年10月までの基本退職金については、旧給付テーブルをもとに計算された額を保全した上、平成14年11月以降は、新給付テーブルをもとに計算された退職金を支給することとなります。
関連ページ
3.退職金等の額の概算
退職金額は、基本退職金と付加退職金の2種類を合算したものであり、退職金の額は、掛金月額と納付月数によって決まります。
例えば、掛金月額10,000円を10年(120月)納付した場合の基本退職金は、基本退職金額表の黄色の太字部分のように1,265,600円、20年(240月)の場合2,666,600円、30年(360月)の場合4,213,100円となり、付加退職金が支給される場合には、上記の基本退職金に加算されることになります。
なお、納付月数が11月以下の場合は、退職金は支給されず(過去勤務掛金の納付があるものについては、11月以下でも過去勤務掛金の総額が支給されます。)、12月以上23月以下の場合は、掛金総額を下回る額に、24月以上42月以下の場合は、掛金総額に、43月以上から運用利息等が加算され、長期加入者に有利ないわゆる“退職金カーブ”の仕組みになっています。
(1) 基本退職金
掛金月額と納付月数に応じて固定的に定められている金額で、制度全体としての利回りを年1.0%として設計し定められた額
(2) 付加退職金
剰余金の状況等に応じて定められる金額。具体的には、掛金納付月数の43月目とその後12か月ごとの基本退職金相当額(仮定退職金)に、厚生労働大臣が定めるその年度の支給率を乗じて得た額を退職時まで累計した総額
■基本退職金額表(平成14年11月改定の基本退職金額です。)
| 納付月数 掛金月額 |
12月 (1年) |
24月 (2年) |
36月 (3年) |
60月 (5年) |
84月 (7年) |
120月 (10年) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,000円 | 7,200 | 48,000 | 72,000 | 121,640 | 173,520 | 253,120 |
| 3,000円 | 10,800 | 72,000 | 108,000 | 182,460 | 260,280 | 379,680 |
| 4,000円 | 14,400 | 96,000 | 144,000 | 243,280 | 347,040 | 506,240 |
| 5,000円 | 18,000 | 120,000 | 180,000 | 304,100 | 433,800 | 632,800 |
| 6,000円 | 21,600 | 144,000 | 216,000 | 364,920 | 520,560 | 759,360 |
| 7,000円 | 25,200 | 168,000 | 252,000 | 425,740 | 607,320 | 885,920 |
| 8,000円 | 28,800 | 192,000 | 288,000 | 486,560 | 694,080 | 1,012,480 |
| 9,000円 | 32,400 | 216,000 | 324,000 | 547,380 | 780,840 | 1,139,040 |
| 10,000円 | 36,000 | 240,000 | 360,000 | 608,200 | 867,600 | 1,265,600 |
| 12,000円 | 43,200 | 288,000 | 432,000 | 729,840 | 1,041,120 | 1,518,720 |
| 14,000円 | 50,400 | 336,000 | 504,000 | 851,480 | 1,214,640 | 1,771,840 |
| 16,000円 | 57,600 | 384,000 | 576,000 | 973,120 | 1,388,160 | 2,024,960 |
| 18,000円 | 64,800 | 432,000 | 648,000 | 1,094,760 | 1,561,680 | 2,278,080 |
| 20,000円 | 72,000 | 480,000 | 720,000 | 1,216,400 | 1,735,200 | 2,531,200 |
| 22,000円 | 79,200 | 528,000 | 792,000 | 1,338,040 | 1,908,720 | 2,784,320 |
| 24,000円 | 86,400 | 576,000 | 864,000 | 1,459,680 | 2,082,240 | 3,037,440 |
| 26,000円 | 93,600 | 624,000 | 936,000 | 1,581,320 | 2,255,760 | 3,290,560 |
| 28,000円 | 100,800 | 672,000 | 1,008,000 | 1,702,960 | 2,429,280 | 3,543,680 |
| 30,000円 | 108,000 | 720,000 | 1,080,000 | 1,824,600 | 2,602,800 | 3,796,800 |
| 納付月数 掛金月額 |
180月 (15年) |
240月 (20年) |
300月 (25年) |
360月 (30年) |
420月 (35年) |
480月 (40年) |
| 2,000円 | 390,000 | 533,320 | 684,160 | 842,620 | 1,009,160 | 1,183,580 |
| 3,000円 | 585,000 | 799,980 | 1,026,240 | 1,263,930 | 1,513,740 | 1,775,370 |
| 4,000円 | 780,000 | 1,066,640 | 1,368,320 | 1,685,240 | 2,018,320 | 2,367,160 |
| 5,000円 | 975,000 | 1,333,300 | 1,710,400 | 2,106,550 | 2,522,900 | 2,958,950 |
| 6,000円 | 1,170,000 | 1,599,960 | 2,052,480 | 2,527,860 | 3,027,480 | 3,550,740 |
| 7,000円 | 1,365,000 | 1,866,620 | 2,394,560 | 2,949,170 | 3,532,060 | 4,142,530 |
| 8,000円 | 1,560,000 | 2,133,280 | 2,736,640 | 3,370,480 | 4,036,640 | 4,734,320 |
| 9,000円 | 1,755,000 | 2,399,940 | 3,078,720 | 3,791,790 | 4,541,220 | 5,326,110 |
| 10,000円 | 1,950,000 | 2,666,600 | 3,420,800 | 4,213,100 | 5,045,800 | 5,917,900 |
| 12,000円 | 2,340,000 | 3,199,920 | 4,104,960 | 5,055,720 | 6,054,960 | 7,101,480 |
| 14,000円 | 2,730,000 | 3,733,240 | 4,789,120 | 5,898,340 | 7,064,120 | 8,285,060 |
| 16,000円 | 3,120,000 | 4,266,560 | 5,473,280 | 6,740,960 | 8,073,280 | 9,468,640 |
| 18,000円 | 3,510,000 | 4,799,880 | 6,157,440 | 7,583,580 | 9,082,440 | 10,652,220 |
| 20,000円 | 3,900,000 | 5,333,200 | 6,841,600 | 8,426,200 | 10,091,600 | 11,835,800 |
| 22,000円 | 4,290,000 | 5,866,520 | 7,525,760 | 9,268,820 | 11,100,760 | 13,019,380 |
| 24,000円 | 4,680,000 | 6,399,840 | 8,209,920 | 10,111,440 | 12,109,920 | 14,202,960 |
| 26,000円 | 5,070,000 | 6,933,160 | 8,894,080 | 10,954,060 | 13,119,080 | 15,386,540 |
| 28,000円 | 5,460,000 | 7,466,480 | 9,578,240 | 11,796,680 | 14,128,240 | 16,570,120 |
| 30,000円 | 5,850,000 | 7,999,800 | 10,262,400 | 12,639,300 | 15,137,400 | 17,753,700 |
※退職金額は、付加退職金が支給される場合には、上記の金額に加算されます。
※掛金月額を変更しない場合の金額です。
関連ページ
4.退職金の計算例
一般的なケースを取り上げます。計算方法は掛金納付月数に応じて計算しますが、掛金納付月数が11月以下の場合は、退職金は支給されません。(通算制度または、他制度からの引継ぎを行っている場合は、11月以下でも支給される場合があります。) なお、死亡退職であって掛金納付月数が12月以上23月以下のときの退職金の額は、納付された掛金総額と同額です。
(1)掛金納付月数23月以下の場合(別表1を用いる)
付加退職金は支払われませんので、基本退職金の額が退職金の額となります。

※「区分掛金納付月数」とは、掛金月額を千円ごとに区分した場合における各区分ごとの納付月数をいい、図では掛金月額ごとの納付状況を帯状に表していることから、「区分掛金納付月数」の各単位を「本」と表記します。
〈退職金の額〉
区分掛金納付月数23月(対応退職金額11,700円)が10本と区分掛金納付月数11月(対応退職金額0円)ですから、
(a)23月 11,700円 ×10本= 117,000円 (別表1)
(b)11月 0円 ×10本= 0円 (別表1)
支給額「a+b」 117,000円となります。
(2)掛金納付月数24月以上42月以下の場合(掛金相当額)
付加退職金は支払われませんので、基本退職金の額が退職金の額となります。

〈退職金の額〉
(a)掛金相当額42月 42,000円 ×10本= 420,000円
(b)掛金相当額11月 11,000円 ×10本= 110,000円
支給額「a+b」 530,000円となります。
(3)掛金納付月数43月以上の場合(別表2を用いる)
基本退職金の額と付加退職金の額の合計額が実際に支払われる退職金の額となります。

〈基本退職金の額〉
区分掛金納付月数100月(対応退職金額104,350円)が10本と区分掛金納付月数50月(対応退職金額50,260円)が10本ですから、
(104,350円×10本)+(50,260円×10本)=1,546,100円となります。
〈付加退職金の額〉
(以下の計算例では各年度の支給率は0.005と仮定します。)
1.年度の付加退職金の額
区分掛金納付月数43月(対応退職金額43,010円)が10本ですから、
(a)43月 43,010円 ×10本= 430,100円 (別表2)(仮定退職金額)
430,100円 ×0.005= 2,151円
2.年度の付加退職金の額
(b1)55月 55,520円 ×10本= 555,200円 (別表2)
(b2)5月 1,000円 ×5月×10本= 50,000円 (別表2)
b1+b2= 605,200円 (仮定退職金額)
605,200円 ×0.005= 3,026円
3.年度の付加退職金の額
(c1)67月 68,310円 ×10本= 683,100円 (別表2)
(c2)17月 1,000円 ×17月×10本= 170,000円 (別表2)
c1+c2= 853,100円 (仮定退職金額)
853,100円 ×0.005= 4,266円
4.年度の付加退職金の額
(d1)79月 81,310円 ×10本= 813,100円 (別表2)
(d2)29月 1,000円 ×29月×10本= 290,000円 (別表2)
d1+d2= 1,103,100円 (仮定退職金額)
1,103,100円 ×0.005= 5,516円
5.年度の付加退職金の額
(e1)91月 94,450円 ×10本= 944,500円 (別表2)
(e2)41月 1,000円 ×41月×10本= 410,000円 (別表2)
e1+e2= 1,354,500円 (仮定退職金額)
1,354,500円 ×0.005= 6,773円
〈退職金の額〉
支払われる退職金の額は、基本退職金の額(1,546,100円)と付加退職金(21,732円)との額の合計額で1,567,832円となります。
関連ページ
5.解約手当金の減額計算例
解約手当金の額の計算は退職金の場合と同様ですが、不正行為による減額のほか、その掛金について掛金助成を受けたもので、一定期間の掛金の納付を怠ったことによって中退共がその契約を解除した場合及び被共済者の同意を得て共済契約者がその契約を解除した場合には、その額が次のように減額されます。 過去勤務掛金が納付されたことのない被共済者については,次のアまたはイのいずれか少ない額が解約手当金の額から減額されます。
ア. 掛金助成を受けた額に相当する額
イ. 解約手当金の額の3割の額(1円未満切り捨て)
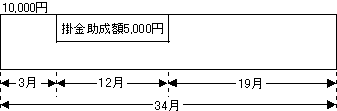
上記の例では、減額のない場合の解約手当金の額は
1,000円 ×34月×10本= 340,000円
掛金助成額相当は
(a) 5,000円 ×12月= 60,000円
解約手当金の額の3割の額は
(b) 340,000円 ×0.3= 102,000円
a<bですから減額される額は60,000円となり、
実際に支払われる解約手当金の額は
340,000円 -60,000円= 280,000円 となります。
6.平成14年10月以前の加入者の退職金等の特例1
基本退職金の予定運用利回りが平成14年11月1日から改定されましたが、同日前に締結された退職金共済契約については、平成14年10月31日に退職したものと仮定した場合の退職金額を保全するため、次に述べる換算月数を用いた上で、改定された基本退職金額表(以下「新給付テーブル」といいます。)をもとに計算された退職金額が支給されることになります。
これを図解すると次のようになります。
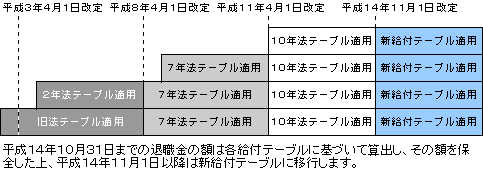
(1)新給付テーブル
平成14年11月以降の掛金に適用される退職金額表です。
(2)旧給付テーブル
平成14年11月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者について、退職金の額に関する経過措置として計算を行うときに用いる次の退職金額の表です。
- 1. 旧法テーブル
平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(旧法契約)の被共済者に適用される退職金額の表です。ただし、平成3年4月以降の掛金の増額部分及び平成8年4月以降の掛金には適用されません。 - 2. 2年法テーブル
平成3年4月1日以降平成8年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約(2年法契約)の被共済者及び平成3年4月1日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で、平成3年4月以降平成8年3月までの掛金増額部分に適用される退職金額の表です。ただし、平成8年4月以降の掛金には適用されません。 - 3. 7年法テーブル
平成8年4月以降平成11年3月までの掛金に適用される退職金額の表です。 - 4. 10年法テーブル
平成11年4月以降平成14年10月までの掛金に適用される退職金額の表です。
7.平成14年10月以前の加入者の退職金等の特例2(換算月数)
平成14年10月までの退職金は、旧給付テーブルをもとに計算された額を保全し、平成14年11月からの退職金は、新給付テーブルをもとに計算された額を支給します。計算方法は、「換算月数」を用い次の順序で行います。
(1) 換算月数の算出
平成14年10月までの納付月数により、旧給付テーブルをもとに退職金を計算します。次に、新給付テーブルにより、上記によって算出された退職金額に最も近く、かつその額を上回る退職金額(直近上位の額)に該当する納付月数を見つけます。平成14年10月までの実際の納付月数と新給付テーブルによる納付月数との差が「換算月数」です。
(2) 基本退職金の計算
その額は、退職月までの実際の掛金納付月数に換算月数を加えた月数によって新給付テーブルを用いて計算します。
(3) 付加退職金を計算します。
(4) 上記(2)と(3)の合計額が退職金額です。
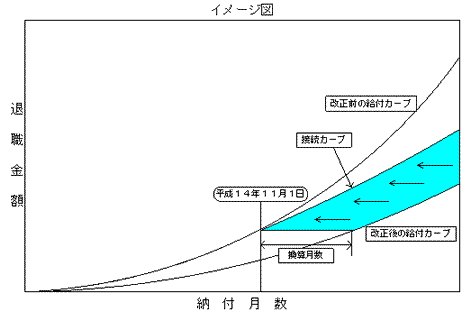
※平成14年11月以降の基本退職金は「納付月数+換算月数」によって算出された額となりこの額の給付カーブが上の接続カーブとなります。
8.適格年金制度からの引継者の退職金計算例
引継額を帯(区分掛金)で通算した部分と残余部分と別々に計算をします。
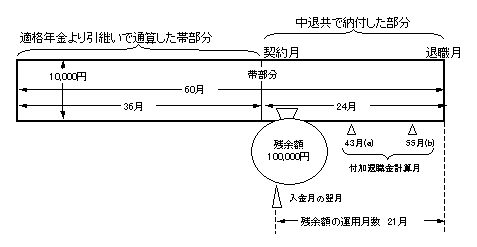
○帯部分
〈基本退職金の額〉
区分掛金納付月数60月の退職金額(別表2)は60,820円(1,000円単位)
60,820円 ×10= 608,200円
〈付加退職金の額〉
※以下の計算では各年度の付加退職金支給率は0.005と仮定します。
- (a)の計算月が属する年度の付加退職金
43,010円 ×10= 430,100円 (仮定退職金)
430,100円 ×0.005= 2,151円 (円未満切上げ)
- (b)の計算月が属する年度の付加退職金
55,520円 ×10= 555,200円 (仮定退職金)
555,200円 ×0.005= 2,776円 (円未満切上げ)
付加退職金額 = 2,151円 + 2,776円 = 4,927円
○残余部分
※以下の計算では残余額の運用利率は0.01と仮定します。
残余額の運用月数21月は1年と9月なので以下の計算となります。
100,000円×(1+0.01)1×(1+0.01)9/12=101,757円(円未満切上げ)
〈退職金の額〉
基本退職金額(608,200円)+付加退職金額(4,927円)+残余部分(101,757円)=714,884円となります。
9.解散存続厚生年金基金からの移換の退職金計算例
解散存続厚生年金基金から中退共へ資産移換をした場合の退職金計算例は、下記のPDFファイルをご参照ください。
なお、従業員が中退共制度に加入した時期が基金解散の前か以後かによって退職金の計算方法が異なります。
Aタイプ
- 基金解散日以後に中退共制度へ加入した場合の計算例 (2ページ/115KB)
Bタイプ
- 既に中退共制度に加入している、又は基金解散の前日までに加入していた場合の計算例(2ページ/110KB)
10.特退共廃止団体からの移換の退職金計算例
特退共廃止団体から中退共へ資産移換をした場合の退職金計算例は、下記のPDFファイルをご参照ください。
なお、従業員が中退共制度に加入した時期が特退共廃止の前か同日かによって退職金の計算方法が異なります。
Aタイプ
- 特退共を廃止した日と同日に中退共に加入して資産移換をする場合の計算例(2ページ/108KB)
Bタイプ
- 特退共を廃止した日より前から中退共に加入していて資産移換をする場合の計算例(2ページ/113KB)
11.合併等に伴う企業年金からの移換の退職金計算例
企業年金から中退共へ資産移換をした場合の退職金計算例は、下記のPDFファイルをご参照ください。
なお、従業員が中退共制度に加入した時期が企業年金の資産移換申出日(資格喪失)の同日か同日より前かによって退職金の計算方法が異なります。
Aタイプ
- 企業年金の資産移換申出日(資格喪失)と同日に中退共制度に加入した場合の計算例(2ページ/113KB)
Bタイプ